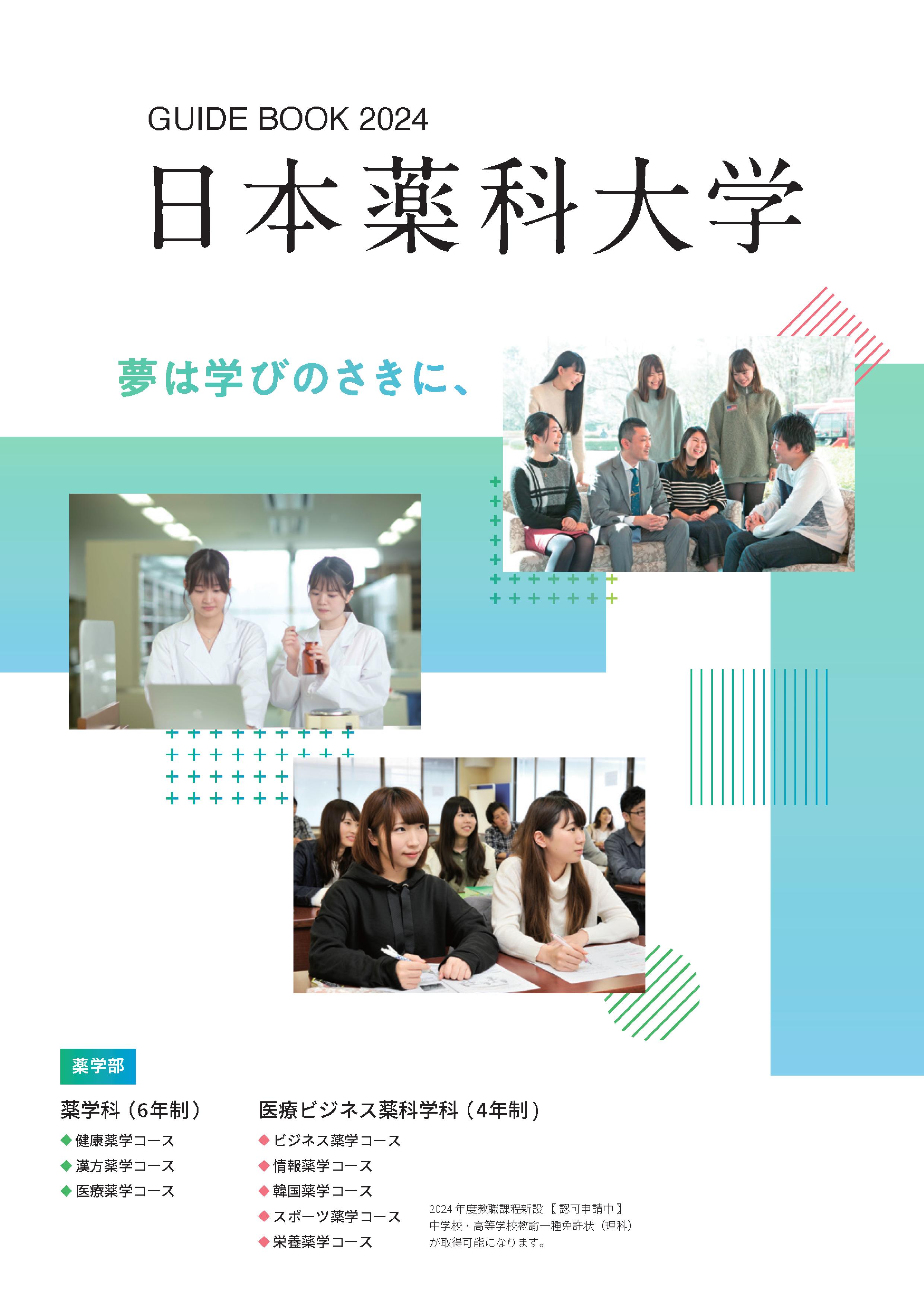「漢方作文・川柳コンテスト2025」 日本薬科大学賞・日本漢方生薬製剤協会賞 受賞者発表
2025年4月~9月にかけて募集いたしました高校生対象の「漢方作文・川柳コンテスト2025」(主催:日本薬科大学、協賛:日本漢方生薬製剤協会)の『日本薬科大学賞』と『日本漢方生薬製剤協会賞』の受賞者が決定しました。
両部門合わせて97名の応募がありました。
ご応募いただきありがとうございました。
【作文部門】
『日本薬科大学賞』
さいたま市立大宮国際中等教育学校(埼玉県) 5年 池田達瑠さん
漢方薬とウェルビーイング
私の母親は漢方薬剤師で、小さい頃から漢方が身近な存在にあった。物心がつく頃から、風邪をひいたり体調を崩したりしたときには、まず漢方薬が用いられてきて、漢方が生活の一部になっていた。今に至るまで学校をあまり休まなかったのも、漢方薬のおかげなのだろうと漠然と感じている。ただ、私自身は漢方薬を飲んで劇的に体調が改善したという経験はあまりない。そこで、今回は父親の経験談を紹介したい。私の父は会社員時代に職場のストレスでパニック障害とうつ病を発症した。当時は心療内科に通い、西洋薬を処方され服用していた。薬で一時的に症状は落ち着いたが、不眠症など副作用が現れたため服用をやめた。その結果、リバウンド症状が出て鬱が悪化した。これを機に西洋薬には限界があると感じたという。
そこで父は母のすすめから、漢方薬を中心に体調を整える取り組みを始めた。体質や症状に合わせた漢方薬を継続的に服用し、食事や睡眠といった生活習慣も見直したことで、少しずつ症状が改善していった。数ヶ月かけて心身のバランスを取り戻し、最終的には通常の生活を送れるまでに回復したのである。この経験を通して、私は西洋薬だけでは対応しきれない問題に対して、漢方薬が有効な補完手段になり得ると考えた。もちろん、西洋薬にも即効性や効果の確実性といった強みがある。一方で、薬に副作用がある場合が多く、また痛み止めのように症状の緩和を期待し、根本の原因へのアプローチが不完全な場合も多い。近年では副作用の少ない治療法や自然由来の方法を考える人が増えてきて、漢方薬への関心も高まっているように思う。
ところで、「ウェルビーイング( well-bling)」という言葉をご存じだろうか。これは「身体的、精神的、社会的に良好な状態にあること」を意味し、単なる病気の有無ではなく、心身の調和や社会とのつながりも含めた幅広い健康のあり方を指す。西洋薬は症状を一時的に抑えることに優れているが、心身全体のバランスを保つという視点では限界があるように感じる。父のように、薬を飲んで症状が緩和されたものの、別の不調が現れたというケースはその一例である。一方、漢方薬は身体全体のバランスを整えることを目的としており、「未病(病気になる一歩手前の状態)」への対応にも力を発揮する。これはまさにウェルビーイングの考え方と一致している。体質や生活習慣に寄り添った形で、根本的な改善を目指す漢方のアプローチは、今後の社会においてますます重要になるのではないだろうか。ストレスや不調を抱えやすい現代社会においては、症状をただ抑えるだけでなく、心身を総合的に整える方法が求められている。私にとって漢方薬は、そうした新しい健康観を支える重要な手段の一つで、今後も身近にある存在として関わっていきたいと考えている。
『日本漢方生薬製剤協会賞』
青森山田高等学校 広域通信制課程(青森県) 1年 千田立煌さん
冬の朝、母が台所で紙袋を開けると、乾いた草の香りが冷たい空気にふわりと広がった。私は床に座り込み、膝を抱えて母の手元をのぞき込む。茶色い粉がさらりとカップに落ち、白い湯気が静かに立ちのぼる。「何を飲んでるの?」と尋ねると、母はやさしく笑って答えた。「五苓散だよ」。ごれいさん。人の名前のようなその響きに、幼い私は「人を飲んでるの?」と不安げにつぶやいた。母は声を立てて笑い、その響きが白いタイルに反射して部屋いっぱいに広がった。笑い声に包まれるうちに、胸のざわめきはしずかに消えていった。五苓散は私にとって、どこか怖く、不思議で、忘れられない存在になった。
それから時は流れ、先日、久しぶりに風邪をひいた。夜中に布団の中で寝返りを繰り返す。鼻が詰まり、頭は熱で膨らむように重い。目を閉じても眠れず、時計の針の音ばかりが耳に響いた。翌朝、ふらつきながら近くのドラッグストアへ向かった。頭がぼんやりとしたまま、色とりどりのパッケージに目を走らせていると、漢方コーナーに「五苓散」の文字を見つけた。
――あ、あのときの。
母の台所の白い湯気と笑い声が、突然目の前に立ち上がった。懐かしさが沁みて、自然に手を伸ばした。けれどその隣に風邪に効くと昔からよく知られる「葛根湯」が並んでいた。店員さんに勧められたこともあり、私はそちらを選んだ。袋を見つめながら、ふと昔の自分を思い出す。幼い頃なら「かっこんとう?エッフェル塔みたいなやつ?」と笑ったにちがいない。
家に戻り、葛根湯を湯に溶かした。草の香りがふわりと立ちのぼり、窓ガラスの曇りをゆらゆらと揺らす。一口含むと、土を思わせる苦みが舌に広がり、じわりと温かさが体にしみ込んでいく。母がよく言っていた「これを飲むと体が楽になるよ」という言葉が蘇った。たしかに、今の私は体の奥からじんわりと温められている。まるで体の中までお風呂に入っているみたいだ。だから「湯」という字がつくのかもしれない。そんなことを考えると、苦みに混じる安らぎが、母の声のようにやさしく胸に広がった。
その夜、布団の中でぼんやりとスマートフォンを眺めていると、神農の話を知った。古代の人で、自分の体を使って草木を試し、効能を確かめたという。あの苦い粉を、何度も自分の口に運び、嘗め続けた姿を思うと胸が熱くなる。命を削ってまで草木を飲み、その力を未来に渡したのだ。そう考えれば、幼い頃人を飲んでいると思った私も、あながち間違いではなかったのかもしれない。草木の命も、昔の人の知恵も、母の笑顔も、確かに私の体の中に飲み込まれているのだから。
湯気の向こうで、母がそっと「大丈夫」と囁く声が聞こえるようだ。苦みの奥の温かさに、遠い昔から続く命のつながりが胸に静かに立ちのぼるのを感じる。そして、また一口、人を飲む。
【川柳部門】
『日本薬科大学賞』
青森山田高等学校 広域通信制課程(青森県) 1年 千田立煌さん
神農の 舌に刻まれ 命の書
『日本漢方生薬製剤協会賞』
東京都立園芸高等学校(東京都) 1年 中越真苗さん
漢方で 咲かす笑顔と 明日の夢
受賞者には後日賞品をお送りいたします。
また、ご応募いただいた皆さまには、参加証をメールにてお送りいたします。

 ENGLISH
ENGLISH SEARCH
SEARCH お問い合わせ
お問い合わせ 資料請求
資料請求 アクセス
アクセス LMS
LMS SNS
SNS


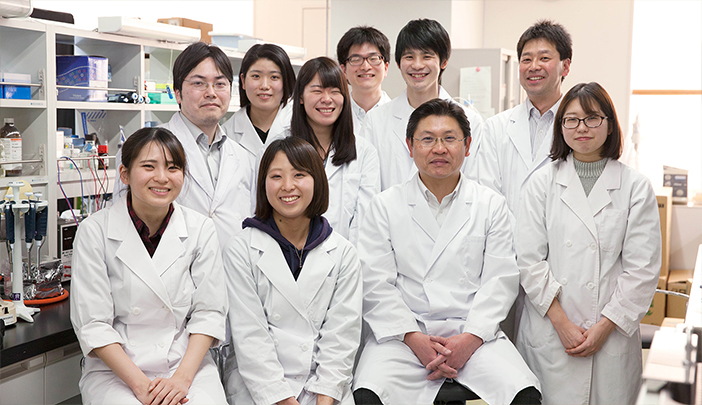
 受験生の方へ
受験生の方へ 在学生の方へ
在学生の方へ 資料請求
資料請求 SNS
SNS ENGLISH
ENGLISH LMS
LMS 交通アクセス
交通アクセス 採用情報
採用情報
 お問い合わせ
お問い合わせ